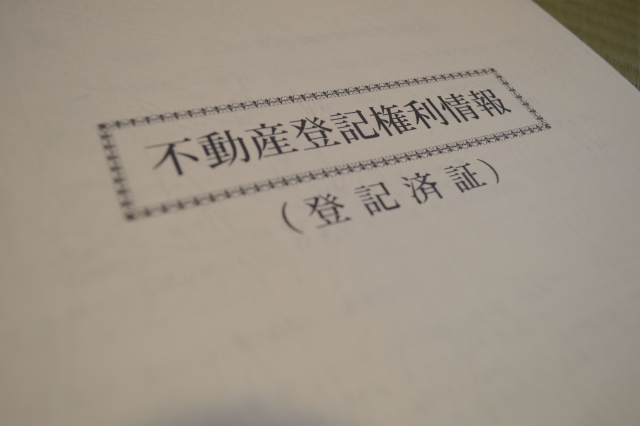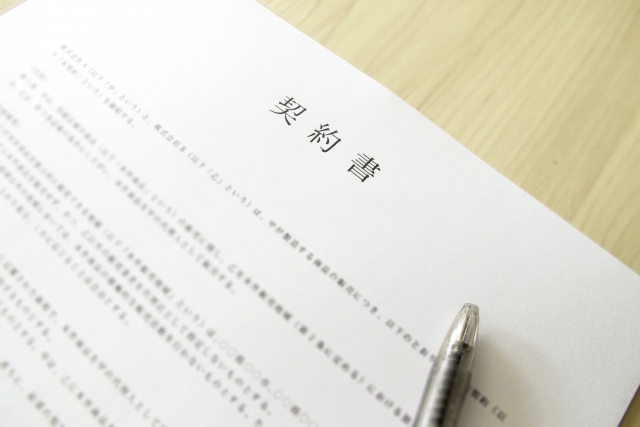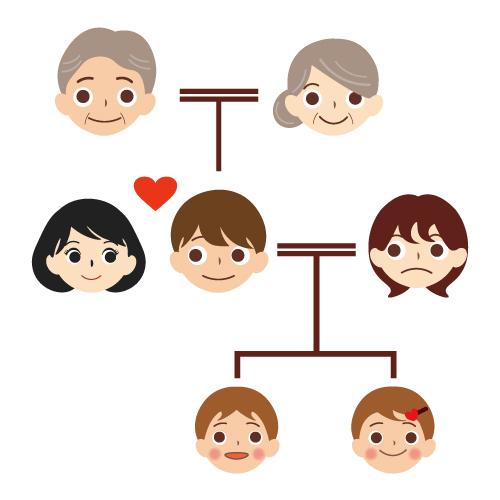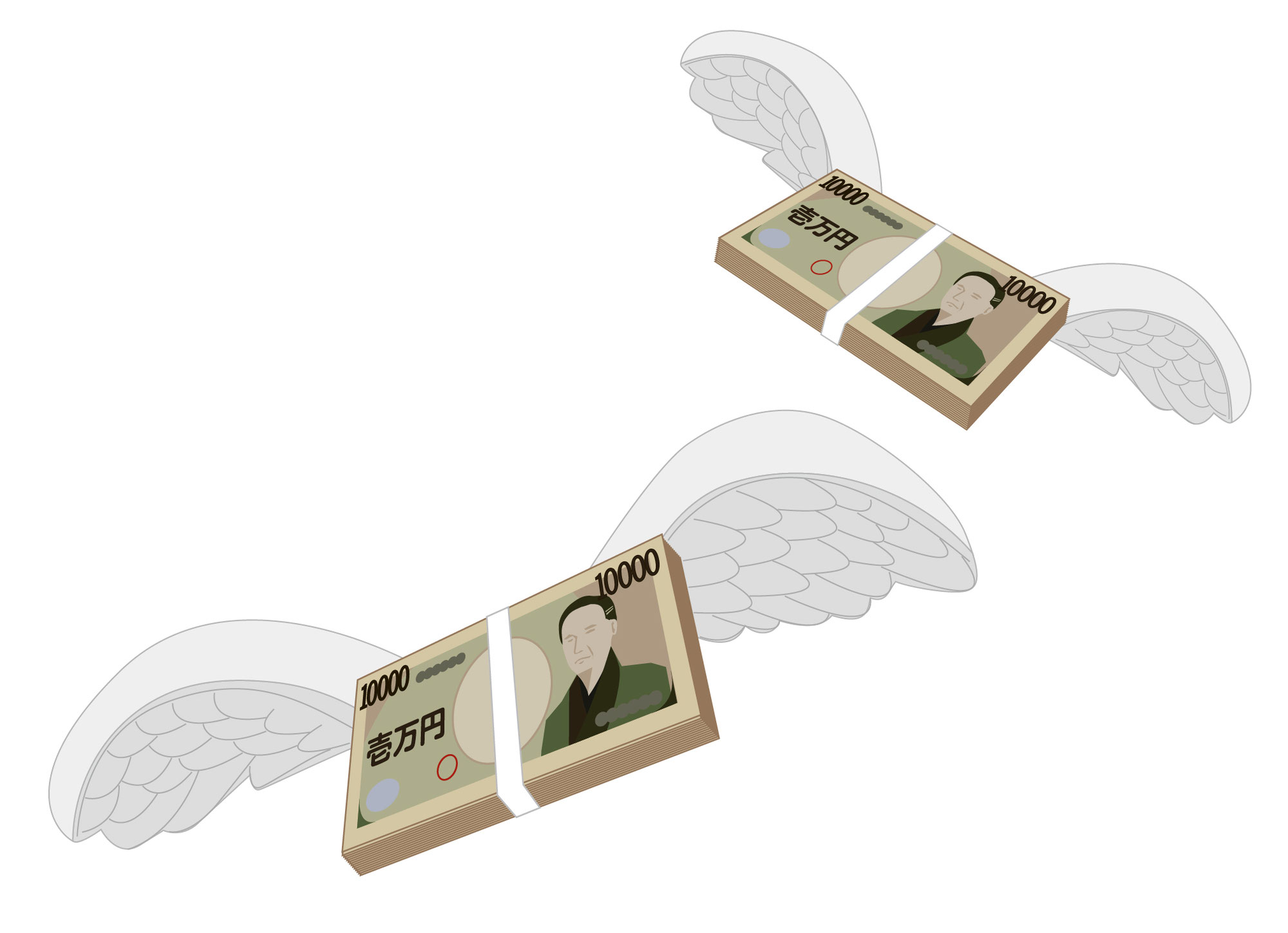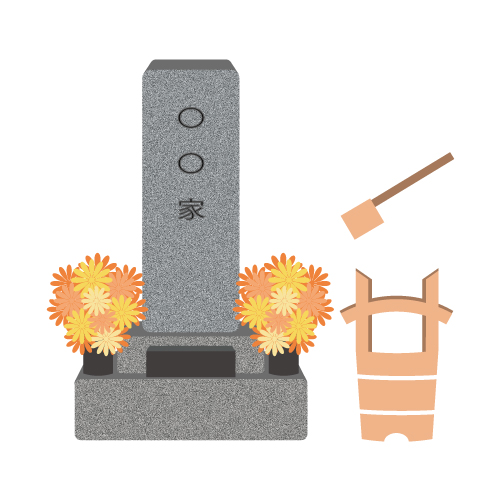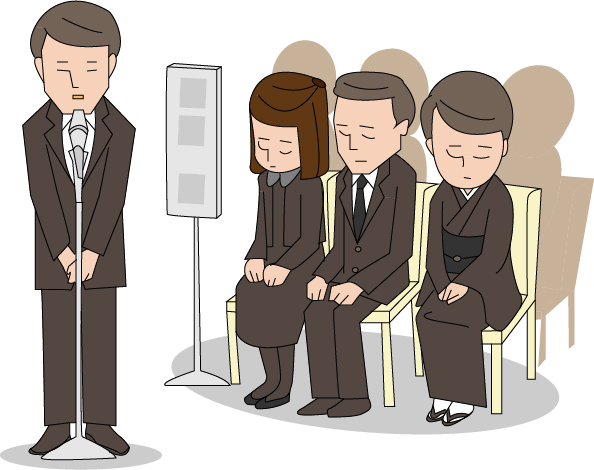2025/06/28
相続登記はいついつまでにしなければならないという決まりはありません。 そもそも、登記自体に義務はありません。 では、相続登記をしないで放っておくとどうなるのでしょうか。 長年相続登記せずに放置しておくと、少し困ったことになってしまうことがあります。 相続人の誰かが亡くなり、権利関係が複雑になってしまう可能性があります。...
2025/06/26
相続税にも税額控除があります。 ・贈与税額控除 被相続人から生前(亡くなる3年以内)に贈与を受け贈与税を支払っていた場合、 その者が支払う相続税額からすでに払っている贈与税額を差引きますよというものです。 ・配偶者の税額軽減 配偶者の相続分が法定相続分までの場合、配偶者には相続税は課税されません。...
2025/06/22
一般的に葬式費用は相続財産から控除できると思われていますが、中にはできない費用もあります。 相続財産から控除できる葬式費用は、、、 ・仮葬式、本葬式費用 ・お通夜、弔問客への食事、酒代 ・葬儀に係るお布施 ・お通夜、葬儀における香典返し ・その他、葬儀前後でかかる費用 一方、控除できない費用もあります。...
2025/06/20
原則として、相続、遺贈、死因贈与により取得された財産はすべて相続税の対象です。 しかしながら、その財産の性質や国民感情等に照らし合わせ、 課税対象としない「非課税財産」がいくつかあります。 この非課税財産の代表的なモノに、墓所、霊廟、仏壇、仏具などがあります。 仏壇、仏具と書きましたが、宗教は問われません。...